|
|
|
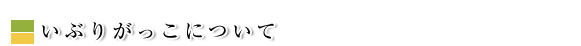
|
いぶりがっことは
|
|
古来伝承の囲炉裏干しの大根漬け(いぶり漬け)
|
|
四方を山々に囲まれた雄勝野(おがちの)は、日照時間が少なく、降雪の時期が早いため、漬け物造りのための秋大根を天日で十分に干すことができません。屋内の梁(はり)につり下げ、囲炉裏火の熱と煙を利用して干し上げて漬け込む”燻り(いぶり)漬け”が造り継がれてきました。囲炉裏火で燻煙乾燥することで風味と保存性が高まり、さらに初冬の低温下で漬け込むことにより、この地方の雪深く長い冬を越してまでも食べることができました。漬け方は様々で、家々の味があり代々造り継がれてきました。その起源は古く室町時代からとも伝えられています。
このいぶり漬けは、幾多の時代を経て昭和30年代に薪ストーブが普及するまで雄勝野のほぼ全戸で造られていました。冬場のなくてはならない常備食として人々の健康を支え、酒の肴やお茶うけとして人々の語らいの場に欠かせないものでした。この地方で大根漬け(でごづげ)といえば、このいぶり漬けのことをいい、冬から春にかけてごく日常の食べ物でした。
|
 昭和35年 雄勝郡 撮影 加賀谷政雄 昭和35年 雄勝郡 撮影 加賀谷政雄 |

|
囲炉裏火とともに
昭和30年代、薪ストーブが普及し、家屋から囲炉裏が消えていくと同時にいぶり漬けも造られなくなっていきました。薪ストーブで乾燥すると大根に『す』が入り、囲炉裏火のように干し上げることができなかったのです。
食べ物が美味しく豊かになっていく時代の流れは、都会から遠くはなれた山里であっても同じでした。素朴な味わいのいぶり漬けは、その役割を終えたかのように、次第に造られなくなっていきました。
|
焚き木干し沢庵
昭和40年代に入るといぶり漬けの味を懐かしむ声が聞こえてきました。漬け物屋を営んでいた先代は家伝のいぶり漬けの商品化を試みます。囲炉裏火の熱と煙で干し上げた大根に『す』入りが起きないことに着目し、厳選した薪を燃した”焚き木干し”による大根の燻煙乾燥を独自の燻製小屋を造り追求しました。また、古来伝承の米ぬかと塩を主体にしたシンプルな漬け込みにこだわることで、いぶり漬け本来の素朴で味わい深い風味を目指しました。
|
 |

登録商標 いぶりがっこ 第1588021号
|
いぶりがっこ発売
そうして試行錯誤を繰り返した末、出来上がったいぶり漬けに、"いぶりがっこ"と名を付し発売しました。"がっこ"とは秋田の方言で漬け物を意味します。
いぶりがっこは人気を得て、特に都会で生活されている同郷の方々が懐かしそうに買ってくださいました。以来、半世紀にわたり多くの皆様に御愛食いただき、きむらやを代表する秋田漬物としてご周知いただいております。 |
山里の風味
ナラの木、桜、ケヤキの広葉樹を燃したあまい香りは、どこか懐かしく囲炉裏火の昔を思わせます。
素朴で自然な風味は雪深い秋田の風土そのもの、人々の暮らしの中から生まれ、数百年の時を経て造り継がれてきた味わいには、山里の情緒がにじみでています。 |

|


|

